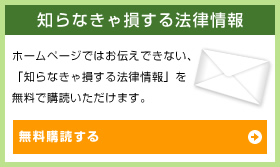東京地方裁判所平成25年10月3日判決
事案の概要
原告が、死亡した連帯保証人Aの法定相続人である被告らそれぞれに対し、求償債権残元金のうち法定相続分4分の1と同額の支払を求めた事案。
争点
① 被告らによる相続放棄の申述が、民法915条1項本文に定める「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」の熟慮期間内にされた有効な相続放棄といえるか。
② 被告らが、被相続人の遺産の一部について遺産分割協議を成立させたことにより民法921条1号本文の「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」にあたるとして単純承認をしたものとみなされる。
争いのない事実
1 B信用金庫のCに対する貸付
B信用金庫は、Aの長男Cに対し、平成8年1月24日、1000万円を次の約定で貸し渡した。
2 Cと原告との間の保証委託契約
原告は、Cとの間に、平成8年1月24日、前記借入れにつき次の内容の保証委託契約を締結し、前記借入れについて連帯保証する旨を約した。
3 Aと原告との間の連帯保証契約
Aは、原告に対し、平成8年1月24日、Cの前記保証委託契約から生じる債務について連帯保証する旨を約した。
4 Aの死亡及び遺産分割協議書の作成
Aは、平成19年3月22日、死亡した。
Aの相続人は、長男であるC、二男である被告Y1、長女である被告Y2、孫である被告Y3の4名であった。
Cと被告らは、平成19年11月25日、Aの遺産のうち土地及び建物について、Cが相続する旨の平成19年11月25日付遺産分割協議書を作成し、平成19年11月30日、AのB信用金庫に対する普通預金7159円と出資金1万円について、Cが相続する旨の平成19年11月30日付遺産分割協議書を作成した。
5 代位弁済
Cが支払を怠ったため、原告は、B信用金庫に対し、平成23年2月23日、残元金を一括代位弁済した。
6 相続放棄の申述受理
被告らは、被相続人Aの相続について、平成23年3月17日に千葉家庭裁判所松戸支部に相続放棄の申述をし、平成23年4月4日に受理された。
3 争点に関する当事者の主張
(1)原告の主張
被告らは、実父であるAの死亡の事実及びこれにより自己が法定相続人となった事実をAの死亡日である平成19年3月22日頃いずれも知ったものと推認される。約4年後にした被告らの相続放棄の申述は、熟慮期間が経過した後にされたものであるから無効である。
遺産分割協議の際、土地建物の登記事項証明書を確認するのが通常であるから、本件保証委託契約に基づく求償債権について、Aが原告に対し前記土地建物を担保提供していたことを認識していたはずである。
そうすると、被告らは、その際、Aが原告に対し連帯保証人となっていたことも認識することができたというべきである。
(2)被告らの主張
被告らは、被相続人Aの連帯保証債務の存在を、平成23年1月19日付の債権者B信用金庫からの催告書により初めて知った。
被告らは、平成19年11月25日に、被相続人の不動産について、Cの「相続放棄のため」との求めに応じて、遺産分割協議書に署名捺印してしまった。当該遺産分割協議書は、被相続人からCへの移転登記のための手段に過ぎなかった。
被告らは、被相続人の財産関係については、遺産分割協議書に示された不動産及びB信用金庫の普通預金、出資金のみと思っており、遺産分割協議書も「相続放棄」のためだから、ということで応じたに過ぎない。また、被相続人の債務については全く知らなかった。
被告らは、以下のとおり、被相続人とは全く別に生活をしていたため、被相続人の債務の調査を行うことが事実上不可能であった。
被相続人は、Cとは、同人の出生以来同居していた。被相続人は、長年工作機械の製造業を営んでおり、長男であるCが被相続人の跡を継いで機械の製造業を承継している。これに対し、被告らは被相続人とは全く別に生計を営んでいた。被告Y2は被相続人の実子であるものの、同居はおろか全く交流がなく、物心ついた時から被相続人に会った記憶がない。被告Y3は、被相続人の孫であるものの、被相続人と同居をしたことはない。被告Y1は、大学卒業後に実家を出ており、それ以来、被相続人とは同居していない。被告Y1は昭和52年10月18日結婚をし、年に数回実家を訪問することはあったものの、父親である被相続人の財産関係については一切把握していなかった。平成7年当時は、被告Y1が結婚をして家庭を築いてから相当程度の期間が経過しており、その間、長男であるCが父親である被相続人の跡を継ぐということから、被相続人の財産関係については全く関心もなく、知らされもしなかった。被告Y1は、被相続人の所有する不動産の存在は知っていたものの、当該不動産は被相続人と同居している兄Cが家業を承継するのだから、当然にその財産も承継するものと思っていた。もちろん、被相続人の債務の存在については、被相続人からもCからも聞かされておらず、一切認識していなかった。被告Y1は、Cの住宅建築については、事前には一切聞かされていなかった。また、その後も、被告Y1はCの自宅購入などの資金繰りを問い質す理由もなかった。
裁判所の判断
1 要旨
被告らは、平成19年3月22日に被相続人Aが死亡した後、平成19年11月25日と同月30日に被相続人の相続財産である土地建物と預金等について長男Cが相続する旨の遺産分割協議書を作成している。
しかし、これらの土地建物と預金等は、相続財産として実質的にみれば無価値であるから、遺産分割協議書を作成しただけでは、被告らが相続財産の存在を認識したとはいえない。
被告らは、平成23年1月19日付のB信用金庫からの催告書を受け取るまでは、Aの債務の存在について知らなかったと認められるから、この催告書を受け取った平成23年1月20日(被告Y1及び被告Y3)又は同月21日(被告Y2)になって初めて、「自己のために相続の開始があったことを知った」というべきである。
したがって、被告らが平成23年3月17日にした相続放棄の申述は、民法915条1項が定める「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」の熟慮期間内に相続放棄の申述をしたものであり、これにより有効に相続放棄がされたものと評価するのが相当である。
また、前記各遺産分割協議書は、無価値な相続財産について、被相続人名義から他の相続人である長男C名義に変更することに法定相続人の立場から協力するために作成された形式的なものにすぎないから、遺産分割協議書の作成をもって、民法921条1号本文にいう「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」にあたるとはいえず、被告らが単純承認をしたものとみなすことはできない。
2 認定事実
被相続人Aは、昭和45年5月10日、土地を売買で取得し、その頃から、同土地上に建物を建築して所有していた。
Aの長男Cは、平成7年11月13日、A所有の前記土地上に居宅建物すを新築し、その新築資金として、平成8年1月22日、住宅金融公庫から1420万の住宅ローンを借り入れたほか、B信用金庫から1000万円の居宅建築資金を借り入れ、土地建物を共同担保とし、Cを債務者として、住宅金融公庫に対して債権額1420万円の1番抵当権、原告に対して債権額1000万円の2番抵当権を設定した。
Aは、Cの原告に対する保証委託契約に基づく求償債務を連帯保証したが、被告Y1は、昭和52年に結婚して以来、Aとは独立した生計を営んで別居しており、Aが前記不動産を所有していたことは知っていたが、平成7年のCの建物新築にかかる前記の資金調達の経緯は知らなかった。
被告Y2及び被告Y3は、AやCとほとんど交流がなく、Aの財産や債務についても全く知らなかった。
平成19年3月22日にAが死亡した後、被告らは、Cから依頼を受けた司法書士の申出を受けて、平成19年11月25日、Aの相続財産である土地建物について、Cが相続する旨の遺産分割協議書を作成し、更に平成19年11月30日、AがB信用金庫に対して有していた普通預金7159円と出資金1万円についてもCが相続する旨の遺産分割協議書を作成した。
B信用金庫は、平成23年1月19日付の催告書により、被告らに対し、連帯保証人であるAの相続人として、融資残金497万9161円と利息・損害金を法定相続分に応じて支払うよう催告し、この催告書は、被告Y1と被告Y3に対しては平成23年1月20日、被告Y2に対しては平成23年1月21日に配達された。
Cは、平成23年2月23日に原告が504万9469円を代位弁済した後、平成23年7月12日、土地建物を売買代金合計950万円で有限会社Dに対して売却して住宅金融公庫と原告に対する債務を返済し、住宅金融公庫と原告の抵当権の登記が抹消されたが、Cの原告に対する債務は、上記売却による返済後においても、474万9469円の求償債権残元金の支払債務が残った。
3 争点に対する判断
被相続人Aが死亡時に所有していた相続財産である土地建物は、Aの死亡時における評価額が、その後の売却額である950万円を超えないと認められるところ、他方で、住宅金融公庫と原告に対し、合計2420万円もの債務額の抵当権が設定されていたのであるから、財産価値を超過する担保設定がされていたことにより、相続財産として無価値であったと認められる。
また、AがB信用金庫に対して有していた普通預金7159円と出資金1万円についても、その金額が極めて小さく、相続のための手続費用等を考慮すれば、相続財産としての実質的な価値は、やはり無価値であったと評価できる。
すなわちAの相続財産である不動産や預金・出資金は、いずれも社会通念上無価値な物であって「財産」とは評価できない。
したがって、被告らは、遺産分割協議書を作成するにあたって、Aの遺産として、上記の不動産と預金・出資金がAの名義で存在することを知ったとはいえるが、それが財産とまでは評価できない以上、そのような遺産分割協議書の作成をもって、被告らが、相続財産の存在を認識したということはできず、したがって、民法915条1項本文にいう「自己のために相続の開始があったことを知った」と認めることはできない。
また、被告らは、上記遺産分割協議書の作成にあたって司法書士から説明を受けているから、その際、これらの不動産の登記事項証明書を確認し、本件保証委託契約に基づく求償債権について、Aが原告に対し抵当権を設定して担保提供していることを知ったはずであると認められる。
しかし、Aが原告に対し、Cの連帯保証人となっていることまでは、登記からは分からないのであって、被告らが、登記を確認したからといって、Aが原告に対し求償債務の連帯保証人となっていることまで認識することができたとは認められないし、このようなことを知ったと認めるに足る証拠はない。
被告らが、平成23年1月19日付のB信用金庫からの催告書を受け取るまでに、本件の連帯保証債務を含むAの何らかの債務の存在を知っていたことを認めるに足る証拠はなく、被告らは、この催告書を受け取った平成23年1月20日(被告Y1及び被告Y3)又は同月21日(被告Y2)になって初めて、「自己のために相続の開始があったことを知った」というべきである。
したがって、被告らが平成23年3月17日にした相続放棄の申述は、民法915条1項本文が定める「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」の熟慮期間内に相続放棄の申述をしたものであり、これにより有効に相続放棄がされたことになる。
また、前記各遺産分割協議書は、「財産」としての価値のない物について、長男Cが相続することを定めたものにすぎず、その法的効力の実際は、Cに名義変更などのA死亡後の手続を依頼した意義を有するにすぎない。すなわち遺産分割協議書でCが相続することを定めた不動産や預金等は、いずれも価値がない物であり、「財産」と評価できないから、民法921条1号本文にいう「相続財産」にはあたらないし、これをCが相続することを定めたことも名義変更の手続を依頼したにすぎないから「処分した」ことにもあたらない。
したがって、被告らが遺産分割協議書を作成したことをもって、民法921条1号本文にいう「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」にあたるとはいえないから、被告らが単純承認をしたものとみなすことはできない。
4 結論
以上によれば、被告らは、被相続人Aの相続について、相続の放棄をしているから、民法939条により、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
Aの原告に対する連帯保証債務を被告らが相続することはなく、原告の被告らに対する連帯保証債務履行請求は、いずれも理由がない。